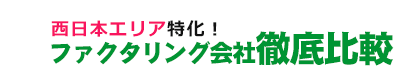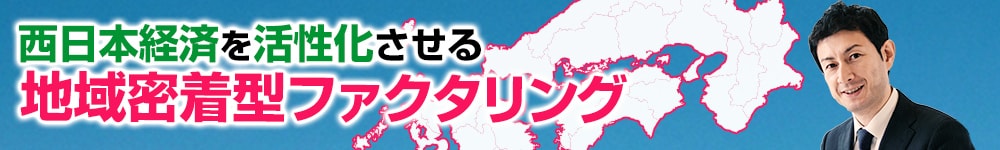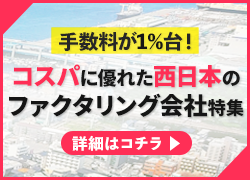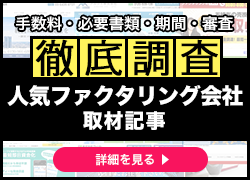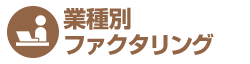中小企業必見!民法改正でファクタリングが円滑になる理由をご紹介
2020年4月1日に施行された民法改正
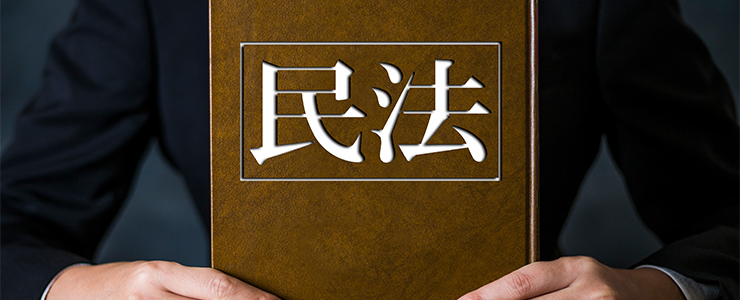
2020年4月1日に、満を持して“契約”に関する民法改正が行われました。
国民にとっては「保証人制度」「賃貸契約」「ネット通販における契約」などの、身近な契約について注目すべき内容が盛り込まれる改正となりましたが、企業にとってどのような影響があるのでしょうか。
当ページでは民法改正が企業に与える環境の変化・ファクタリングへの影響についてご説明していきたいと思います。
債権譲渡禁止特約について

特に“債権譲渡禁止特約”に関わる変更については大きな影響があると予想されます。
なぜならば、債権譲渡禁止特約は、権を所持している企業が第三者に対して債権を売り渡したり、委譲したりといった行為を制限する機能があるためです。
これまでは多くの債権、特に"売掛金"には債権譲渡禁止特約が付与されている場合が多かったのですが、今回の民法改正で債権譲渡禁止特約の扱いが以下の通り変更されました。
改正された第466条第2項の内容
今回の民法改正で手が加えられた条文は、第466条の第2項“債権の譲渡性”です。
第466条第2項
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示( 以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
引用部分を要約すると「債権の譲渡を禁止するという約束があった場合でも、債権の譲渡を禁止する強制力は働かない」という解釈ができます。
つまり、債権譲渡禁止特約が付与された売掛金でも売却を行えるという取り決めです。
大企業との取引において、債権譲渡禁止特約が付与されている場合が多かったため、立場の弱い中小・小規模企業にとっては、まさに救世主とも言えるのではないでしょうか。
追加された第3項と第4項の内容
また、ファクタリングを利用する事業者ならば、新設された「第3項」「第4項」も併せて注目しておきたい変更点です。
第466条第3項
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
まず、第466条の第3項は債務者が支払い先を明確にするための一文です。
債権譲渡禁止条約が付与された売掛金が譲渡された場合、債権を譲渡された企業(取引先)がファクタリングの事実を聞かされていなければ、ファクタリング会社に支払う必要が無いと解釈できます。
しかし、支払いは元々の債権者、つまりファクタリング利用企業に行う必要がありますので、支払いそのものを免れるというわけではありません。
そのため、お金を受け取ったファクタリング利用企業は、ファクタリング会社に受け取った売掛金を引き渡す必要があります。
次に、第466条の第4項を見ていきましょう。
第466条第4項
前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない
第3項で規定されているように最終的に債務者は債権者に代金を支払わなければいけませんが、第4項では、債権者の支払い催促に応じない場合は再び第三者に請求を行う権利が復活する旨の記載がなされています。
つまり、わかりやすく言えば「3者間ファクタリング」と同様、ファクタリング会社は独自で請求が可能となるのです。
ファクタリングの価値は更に高まる

今回の民法改正により、これまで暗黙のルールとされていた契約上の約束が明文化された形です。
一個人としてはまだ実感が薄いかもしれませんが、事業者にとっては“ファクタリング”という有効的な資金調達手段の活発化に繋がる大きな改正になったと言えます。
経営に携わる方は、是非民法の改正点についてご一読ください。
【参考】法務省 民法改正
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html