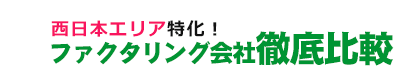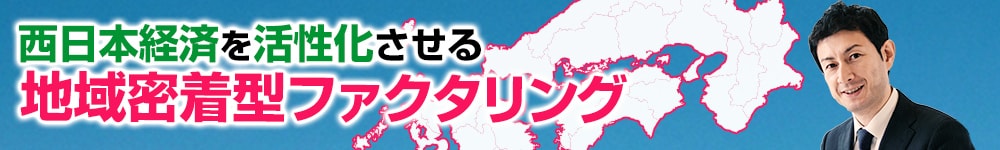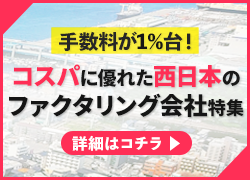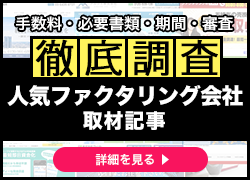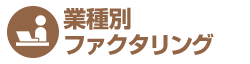持続化給付金とは-知っておきたいファクタリングとの違いと制度概要
持続化給付金とファクタリング
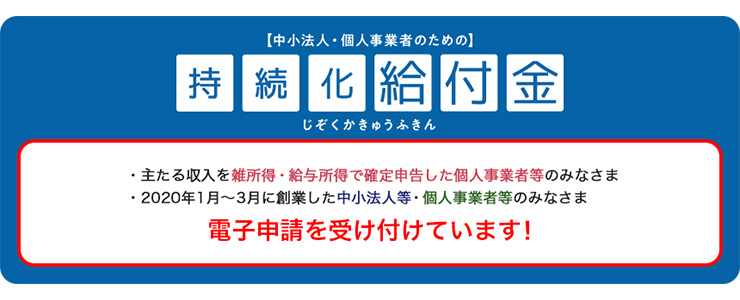
コロナウイルスの大流行に伴い、国は中小企業向けの特別給付金の交付を決定しました。
申請に必要な書類・受給要件・受け取りまでのフローチャートといった「制度の概要」をはじめ、ファクタリングとの利用方法の違い等について解説いたします。
持続化給付金とは
持続化給付金とは、資本金10億円以上の大企業を除いた中小企業やフリーランスを対象とした、文字通り「事業の継続を目的とした給付金」です。
給付の上限金額は法人が200万円・個人事業主が100万円までとなっており、受給できれば事業のピンチを脱出するための大きなカギとなり得ます。
申請は原則としてPC又はスマートフォンから行う形(電子申請)ですが、これらの機器を保有していない方のために、例外として特設の申請会場も設けられています。
申請先や申請書類、具体的な受給要件は以下の通りです。
| 申請先 | 経済産業省 |
| 申請に必要な書類 |
確定申告書類 対象月の売上台帳等 通帳の写し |
| 受給要件 |
資本金が10億円未満かつ従業員数が2000人以下であること。 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。 |
| 申請期間 | 令和2年5月1日から令和3年1月15日まで |
給付までの流れ
給付までの流れは以下の通りです。(電子申請)
(1)添付する申請書類の準備をする。
(2)公式サイトにて仮登録を行う。
(3)届いたメールにアクセスし本登録を行う
(4)ID・パスワードを入力しマイページを作成する。
(5)マイページから情報を入力し書類をアップロードする。
(6)申請先に於いて申請内容が確認される。
(7)不備が無ければ登録した口座に給付金が送金される。
※現在申請は締め切られています。
(1)~(6)までは申請者側が行う手続き、(7)以降は行政が行う手続きになります。
審査期間は2週間程度となっており、中には1週間ほどで振り込まれたという事例も報告されています。
瀕死の状況となった中小企業を救うための制度であるため、スピードを重視した運営がなされているようです。
申請はプロに依頼するべきか
必要書類も少なめ)となっています。
操作説明動画を用意するなどの対策もしており、しっかりと確認すればプロに頼らずとも申請することは十分に可能です。
ただし、こちらはPCやスマートフォンを保有していることが前提になりますので、もしもこれらの機器を保有していない場合は、プロに代理してもらう・直接窓口に足を運んで申請する等の対策が必要でしょう。
ファクタリングとの差別化
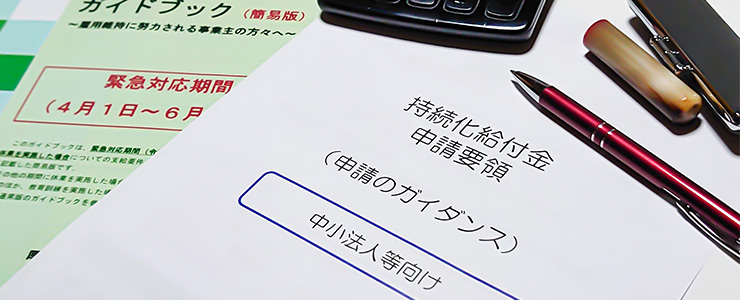
スピード面を重視するのであれば、ファクタリングも有効な手段です。
しかしながら、ファクタリングはあくまでも売上の前払い(売掛金の売却)であり、お金をタダで受け取る訳ではありません。
また、コロナ禍で売上が大きく下がっている状況においては、ファクタリングに利用できる未収金や売掛金が少ないという事情も考慮する必要があります。
ファクタリングはつなぎ資金として非常に高いパフォーマンスを誇る言わば特効薬のような役割を果たしますが、反復継続した利用は企業そのものの破滅を招きかねません。
ファクタリングは資産の売却、持続化給付金は支援金である点で大きく異なります。
給付金が入るまでの「つなぎ」として活用
このように、ファクタリングと持続化給付金は性質が大きく異なるため、一概にどちらが優れているかと評することはできません。
ファクタリングにはファクタリングの利用方法、持続化給付金には持続化給付金の利用方法があるためです。
したがって「シーンによって使い分ける」のが最も賢い選択だと考えます。
例えば、持続化給付金は申請から入金まで2週間程度のタイムラグがありますが、ファクタリングは早ければ当日中の入金も可能です。
持続化給付金の入金を待つ間のつなぎとしてファクタリングを利用してみるのも一つの手ではないでしょうか。